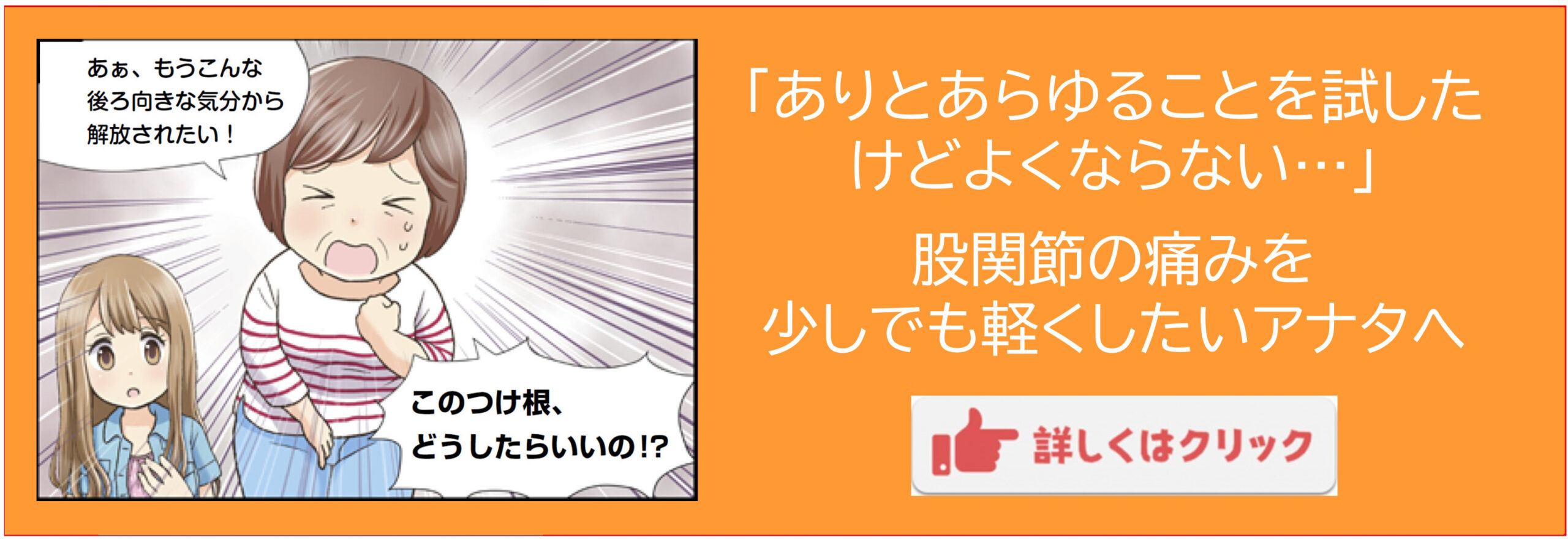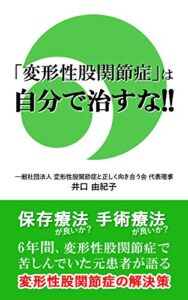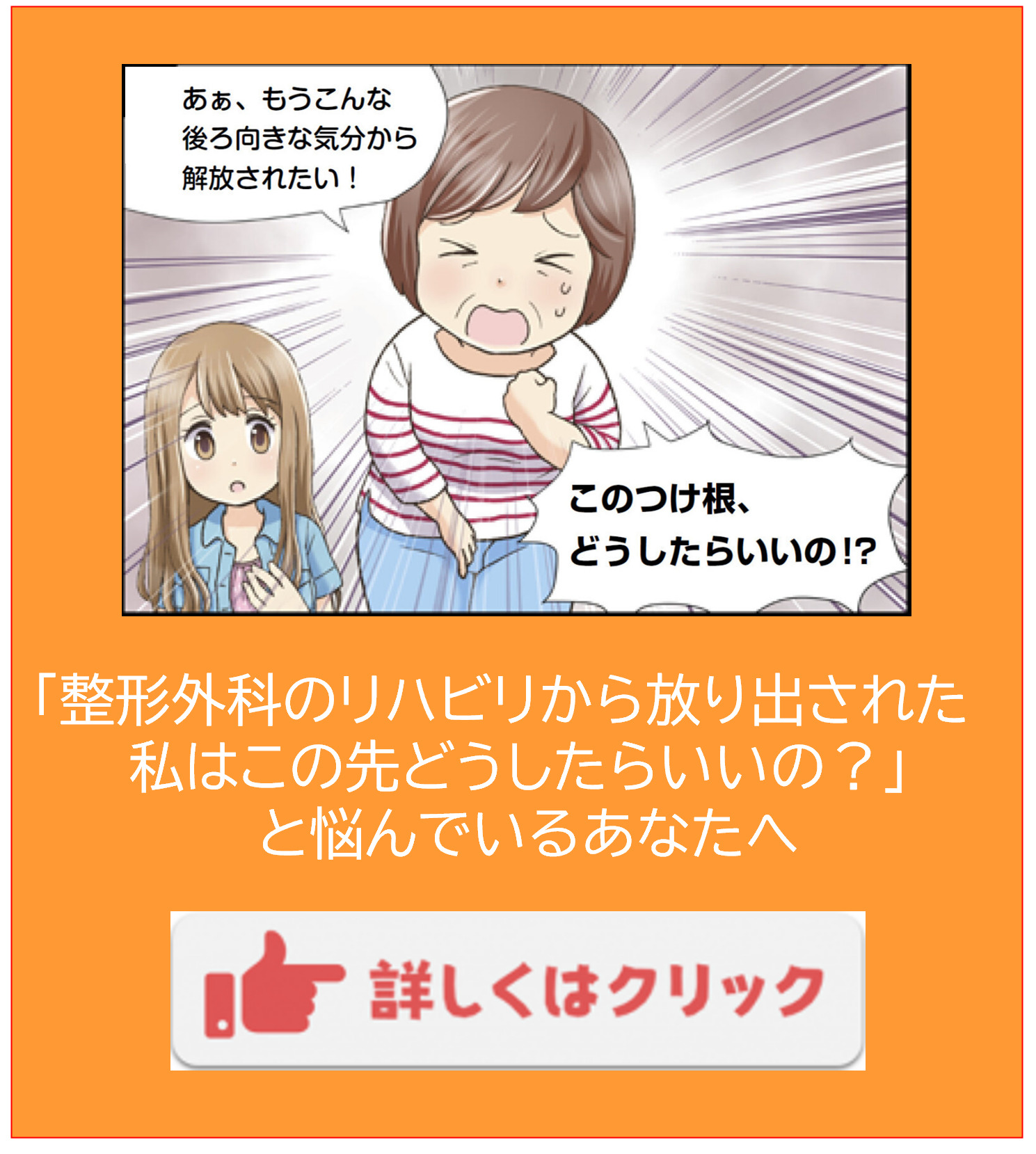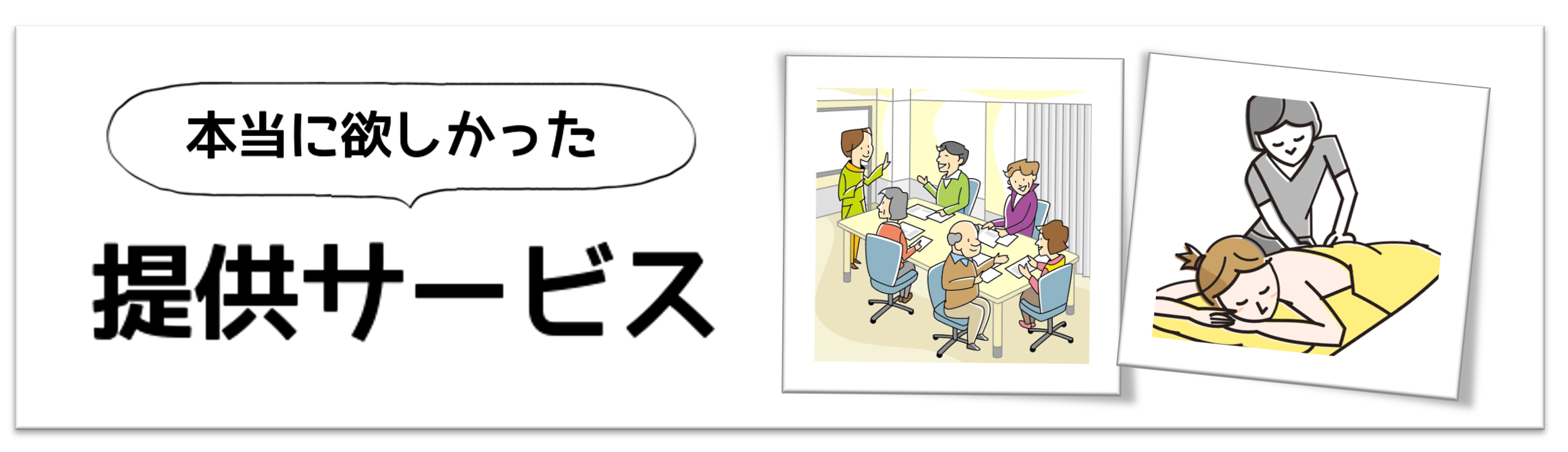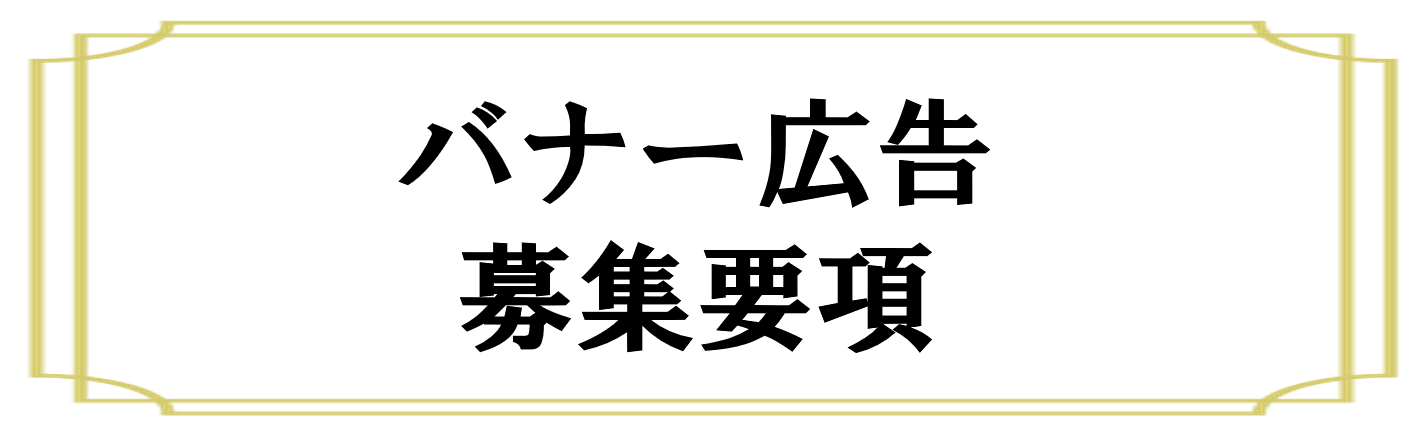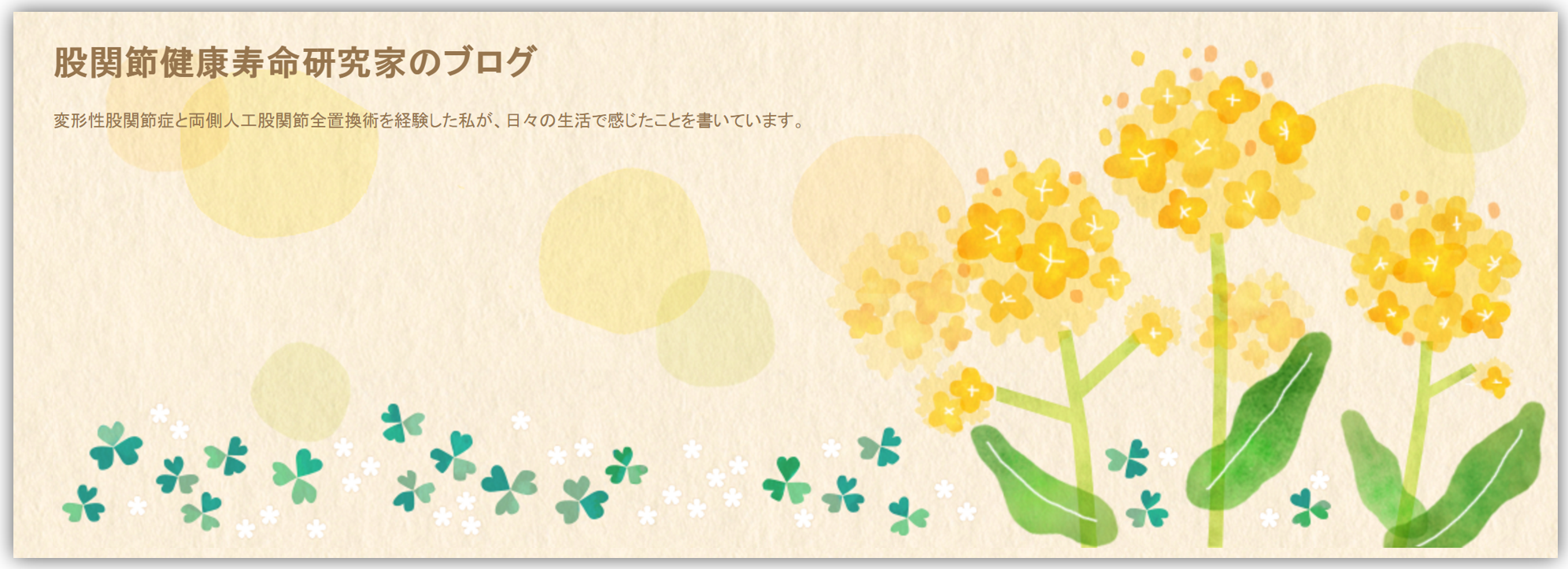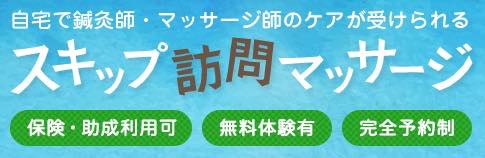変形性股関節症と正しく向き合う会 代表理事の井口です。
2025年10月24日(金)から25日(土)にかけて、下関で開催された第52回日本股関節学会学術集会に参加してきました。
人工股関節手術、リハビリ、筋力、歩行、QOL(生活の質)など股関節に関連する多数の研究結果が発表され、非常に学びの多い2日間でした。
今回は
学会で発表された多数の研究の中から、変形性股関節症の患者が知っておくべき研究や生活の質を高めるヒントになる研究を9つ選びました。
長くなるため、前半・後半の2回に分けてお伝えします。
まずは9つの研究内容のうち4つです。(後半はこちら)
ぜひご覧ください。
1つ目
まずは「人工股関節全置換術後、早期において中殿筋への侵襲(この場合は手術)の違いで歩行自立期間に差が生じるか」という研究。
これは、人工股関節の全置換手術ではALSアプローチやHardingeアプローチが使用されるが、
・ALSアプローチは、Hardingeアプローチと比較して歩行開始やT杖歩行自立までの期間が有意に短い
・結果として在院日数の短縮につながる可能性がある
というものになります。
人工股関節手術のアプローチ方法についてはこちらの記事でもまとめてありますが、上記内容には専門用語が多いので、少し解説しておきます。
ALSアプローチ
ALSアプローチとは、太ももの前外側から皮膚を切開する「前外側アプローチ」の略称です。
手術の際、股関節の外側にある中殿筋と大腿筋膜張筋の間を、筋線維に沿って切開・剥離して進入し、置換対象の股関節に到達する方法です。
分かりやすく言えば、股関節の筋肉を切って股関節に到達するのではなく、筋肉を傷つけないよう「筋肉の隙間をそっと通って股関節に到達する」というイメージです。(あくまでイメージするための記述なので、医学的に正確な表現ではない点をご了承ください。)
後方アプローチのように股関節の後ろ側の筋肉(殿筋群)を切離しないため、動きに制限がでにくいのが特徴です。
Hardingeアプローチ
股関節の外側から入っていく「外側アプローチ」の代表的な方法の1つです。
股関節の安定に関わる中殿筋と小殿筋の一部を、大腿骨の大転子付着部で切離する方法です。
分かりやすく言えば、ALSアプローチが「筋肉の隙間をそっと通って股関節に到達する」のに対して、「筋肉を切って、切った筋肉をめくって股関節に到達する」という感じになります。(こちらも、あくまでイメージするための記述です。)
T杖
持ち手がアルファベットの T字型 になっている杖のことです。
2つ目
2つ目は「人工股関節全置換術後2年間における股関節周囲筋の変化」という研究です。
これは、mini-oneアプローチにおける人工股関節全置換術では、
・術後1年までは股関節周囲筋のCSA(筋肉の量)は回復する傾向
・CT値(筋繊維の密度)は2年かけて増加する傾向
を示し、そこから
・筋量とともに筋繊維密度の改善が、術後1年以降も継続する可能性がある
というものになります。
もっと簡単に言えば、筋肉量だけではなく筋肉の質も重要だということが言えます。
術前からリハビリに取り組むことや食べ物にも気を使うことが重要です。
2つ目も専門用語が多いので、以下に解説します。
mini-oneアプローチ
従来より皮膚切開を小さくし、股関節周囲の筋肉や腱への侵襲(ダメージ)を最小限に抑えることを目的としたアプローチ方法。主に「最小皮膚切開MIS」の初期形式になります。
CSA(Cross Sectional Area)
筋肉を横からスパッと切った形で見たときの“筋肉の面積”を測ることで、筋肉の量を正確に評価するための指標です。
CT値(Computed Tomography value)
CT検査で測定される組織の密度(詰まり具合)を数値化したもので、主に骨の質(骨密度)を評価するための指標です。股関節周囲筋の密度をみる目的でも使われます。
3つ目
次は「人工股関節全置換術後の歩行練習開始日は術後の疼痛及び身体機能と関連するか」という研究です。
この研究では、人工股関節全置換術後の歩行練習の開始日が、術後の疼痛にも身体機能にも在院日数にも影響しないという結論が出されています。
患者さんの中には「早く歩く練習をしたほうがいいのでは?」と考える方もいらっしゃいますが、この研究によれば、無理に早く始める必要はなく、痛みや体調に合わせて進める方が安心、ということになります。
4つ目
最後は「術前サルコペニアを有する60歳以上における人工股関節全置換術の転帰」という研究。
”転帰”というのは病気や怪我の治療が最終的にどのような結果や状態になったかを指す言葉ですが、この研究では
・術後の快適歩行速度はQOL(生活の質)に影響する
・術前にサルコペニアがあると、その快適歩行速度に影響が出る可能性がある
・だからこそ手術前に患者がサルコペニア(加齢などに伴い、筋肉量や筋力、身体の活動能力が低下した状態)になっているかどうかを把握することが重要だと考えられる
ということを伝えています。
術前の筋肉量が、術後の快適さや生活の質にもつながるという点は全くの同感です。
この研究の指摘は、患者さんにとって非常に大切な視点だと感じました。
今回は
第52回 日本股関節学会学術集会で学んだことから、私が重要だと感じた9つの研究のうち4つをシェアしました。いずれも、変形性股関節症の患者が知っておくべき内容です。
一見難しい内容に感じるかもしれませんが、何回も読み直すと理解できるようになります。
後日、後半の記事として残る5つの研究をシェアします。
ぜひ楽しみにしていてください。
患者目線から見たお役立ち情報を知りたい方へ
メールアドレス入力するだけで
定期配信するブログ記事とyoutube動画をすぐにご覧いただくことができます。
ぜひご登録下さい。