
変形性股関節症と正しく向き合う会の代表理事、井口です。
私は、2019年11月から減量に取り組んでいます。
というのも、人工股関節をできるだけ長持ちさせたいから。
加えて、写真に太った姿で写るのがイヤだった、ということもあります。
こちらのほうが大きいかも知れませんが。笑
今日は、そんな”変形性股関節症の患者にとっての減量のお話”です。
気になる方は、ぜひご覧下さい。

変形性股関節症と正しく向き合う会の代表理事、井口です。
私は、2019年11月から減量に取り組んでいます。
というのも、人工股関節をできるだけ長持ちさせたいから。
加えて、写真に太った姿で写るのがイヤだった、ということもあります。
こちらのほうが大きいかも知れませんが。笑
今日は、そんな”変形性股関節症の患者にとっての減量のお話”です。
気になる方は、ぜひご覧下さい。
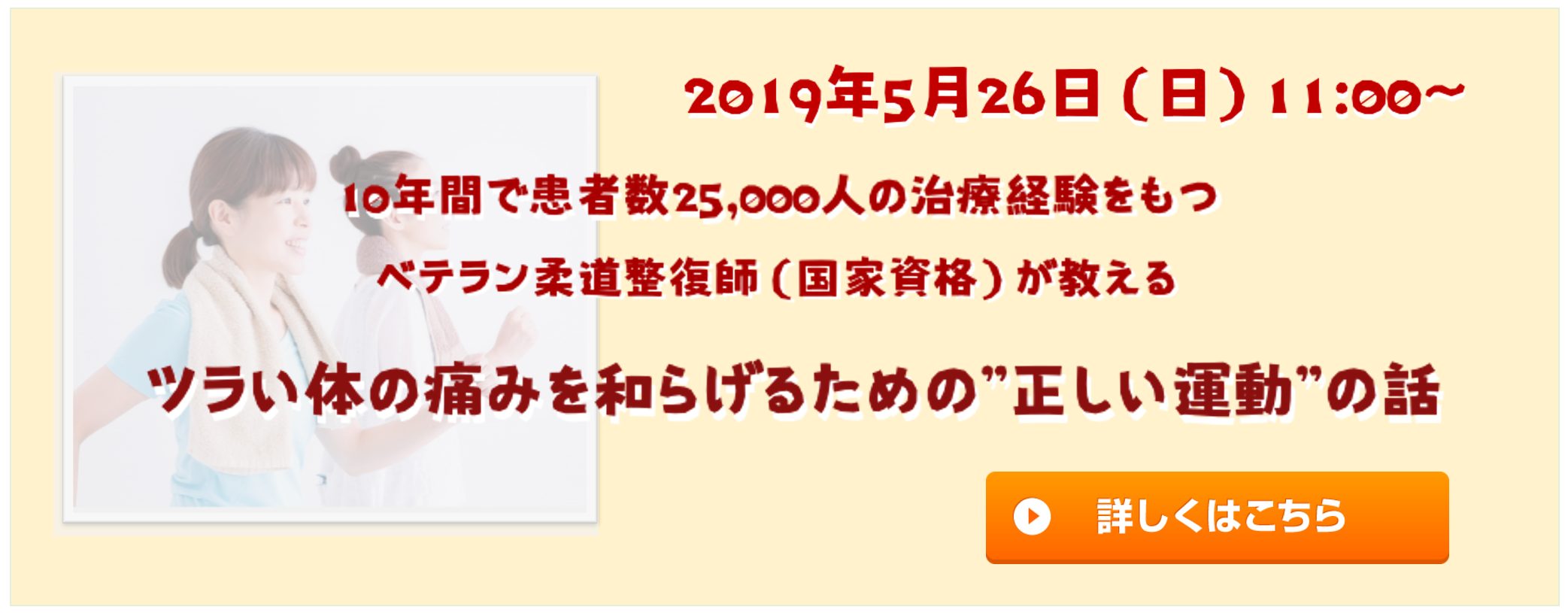
変形性股関節症と正しく向き合う会の代表理事、井口です。
テーマは、「ツラい体の痛みを和らげるための“正しい運動”の話」です。
このテーマで開催するのは、今回で2回目。
今回は、10年間で患者数25,000人の治療実績のあるベテラン柔道整復師を講師にお迎えします。
さらに、参加された方の個別の病状に合わせた“正しい運動”のやり方を具体的にお伝えする個別指導も行います。
そんな”運動”をテーマにした特別セミナー。
今日は、なぜそんなセミナーをやろうと思ったかをお伝えしようと思います。
「正しく運動すれば、股関節の痛みは軽くなる」
このフレーズにピンときた方は、ぜひご覧ください。

変形性股関節症と正しく向き合う会の代表理事、井口です。
変形性股関節症の「保存療法」。
変形性股関節症と診断され、保存療法に取り組んでいる方も多いのではないでしょうか。
今日は、保存療法についての3つのポイントをお伝えしようと思います。
日々の保存療法への取り組みのヒントになれば幸いです。

変形性股関節症と正しく向き合う会の代表理事、井口です。
桜の花も咲き、すっかり春めいてきました。
そして、もうすぐ新しい元号「令和」になります。
今日は、節目であるこの時期にぜひ意識していただきたいことをお伝えしようと思います。
それは「股関節の運動と股関節ケアの両輪」の話。
股関節の運動は股関節ケアとセットで行うことで非常に効果がでるよ、ということ。
これまで何度もお伝えしてきたテーマです。
ただ、まだまだ伝わっていないと実感することが多いこのテーマ。
変形性股関節症で悩む人にどうしてもお伝えしたいです。
ぜひご覧下さい。

変形性股関節症と正しく向き合う会の代表理事、井口です。
今年も残りあと少しとなりました。
今日は、今年中にどうしてももう一度お伝えしたいことを書こうと思います。
それは「股関節の運動と股関節ケアの両輪」の話。
股関節の運動は股関節ケアとセットで行うことで非常に効果がでるよ、というお話です。
非常に大事であるにも関わらずまだまだ伝わっていないこのお話。
変形性股関節症で悩む人を減らすために、どうしてもお伝えしたい内容です。
ぜひご覧下さい。

変形性股関節症と正しく向き合う会の代表理事、井口です。
私がいつも伝えたいこと。
その一つに「退院後も継続してリハビリに取り組むことが本当に重要」ということがあります。
このことは何度もお伝えしてきた内容ですが、今日は少し視点を変えてお伝えします。
それは
「もし私が退院後に継続してリハビリを続けていなかったら何が起こっていたか?」
ということ。
もしリハビリを継続していなかったら起こるであろうことを3つ挙げてみました。
逆説的ですが、リハビリを継続し続けることの重要性を少しでも感じていただければ幸いです。

変形性股関節症と正しく向き合う会の代表理事、井口です。
今日は、股関節の運動と股関節ケアをセットで行うことの重要性について、再度お伝えしようと思います。
というのも、日々変形性股関節症の相談を受ける中で、「股関節の運動は股関節ケアと両輪で回す必要がある」という非常に大事なポイントがまだまだ伝わっていない、と感じるから。
これは、変形性股関節症に立ち向かうために絶対に欠かせないお話です。
ぜひご覧下さい。

変形性股関節症と正しく向き合う会の代表理事、井口です。
変形性股関節症と診断されたアナタ。
直後のショックから何とか立ち直り、情報収集を始めてわかるのが「変形性股関節症患者は、股関節周辺の筋肉を強化することがすごく大事」ということ。
そんな状況を少しでも改善しようと、運動を始める方は多いです。
今日は、そんなアナタへのお話です。
少しでも自分に当てはまると感じた方は、ぜひご覧下さい。