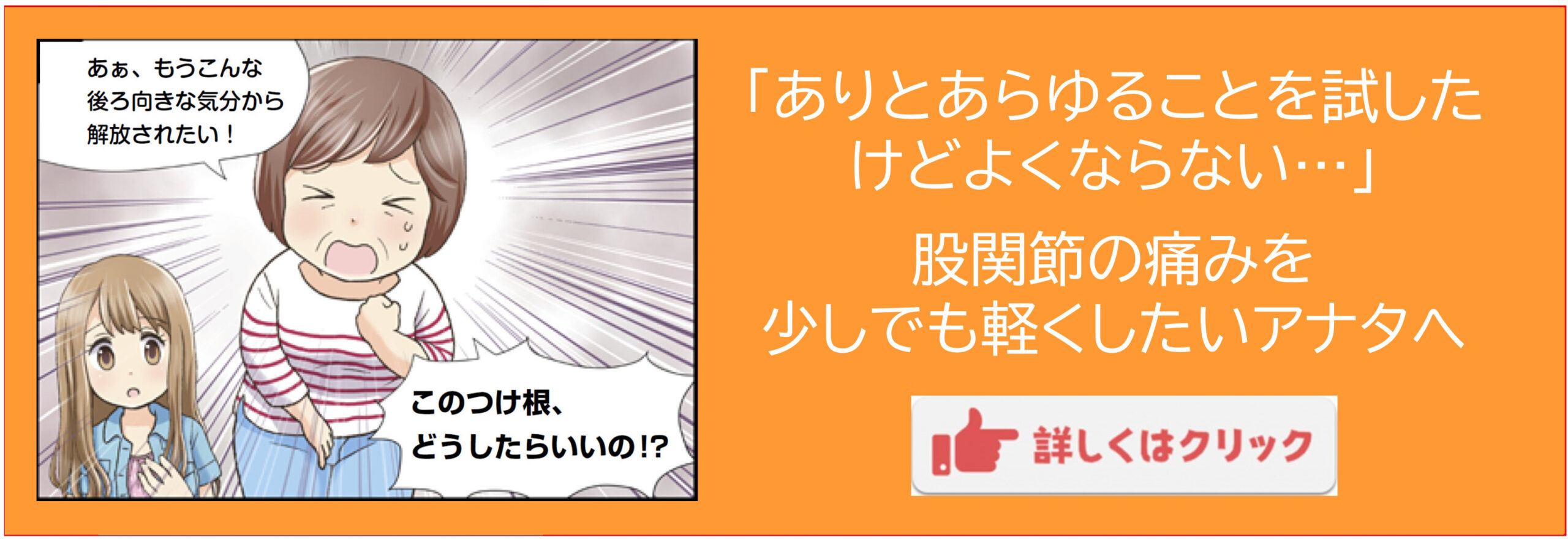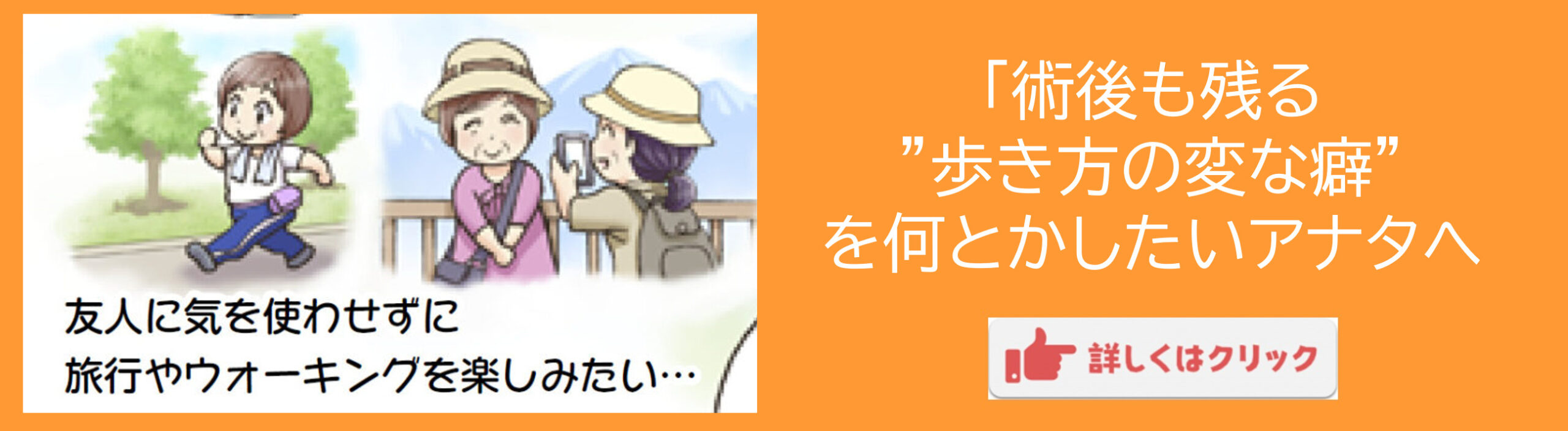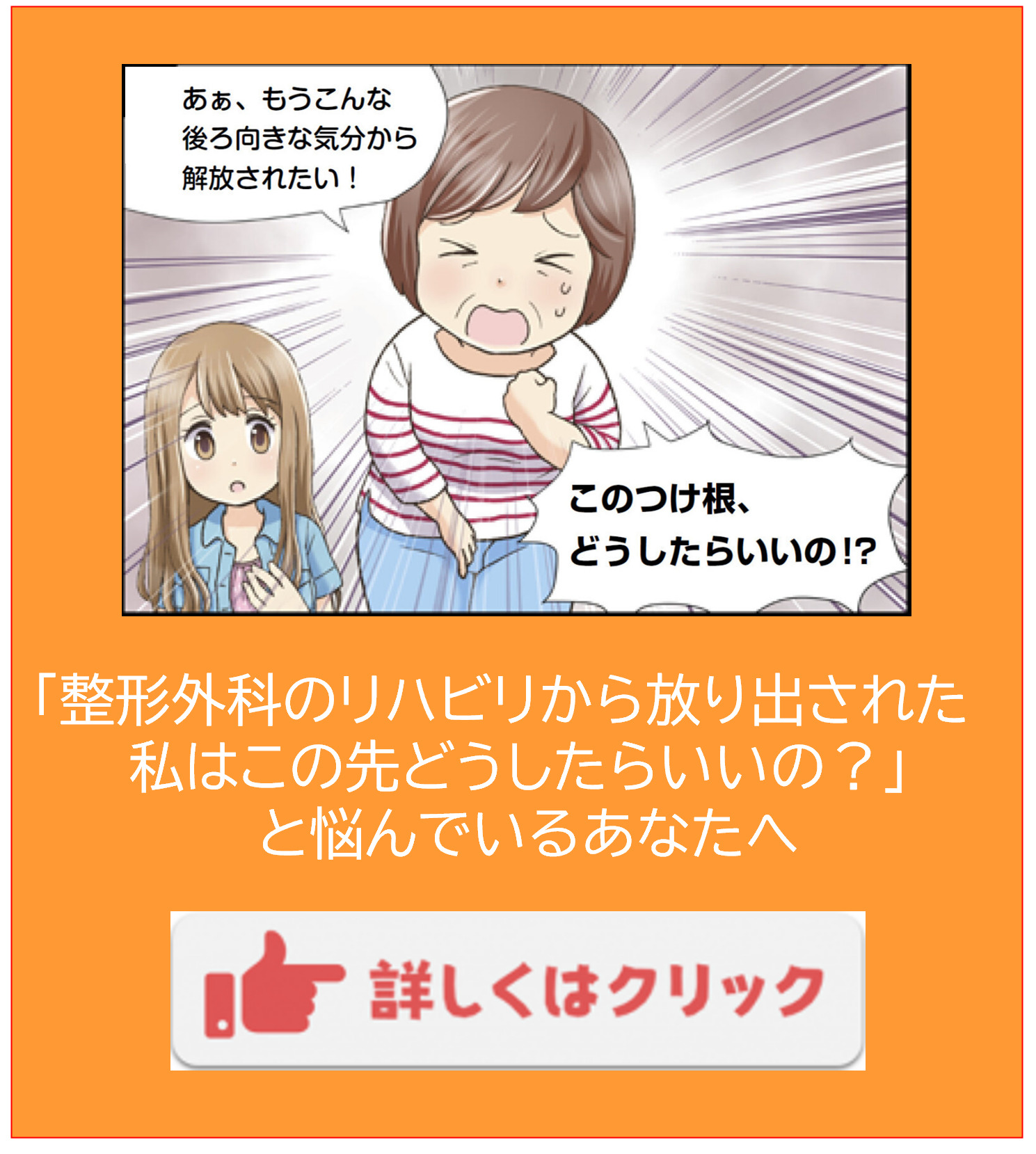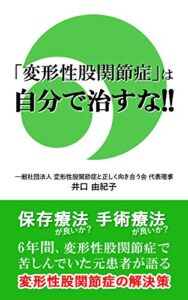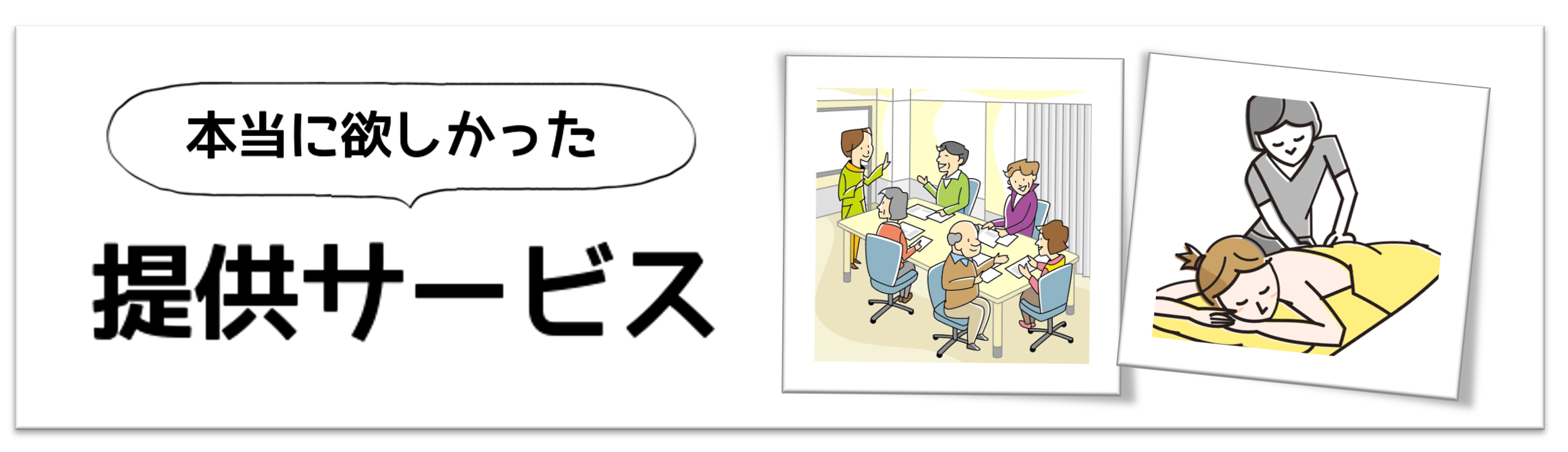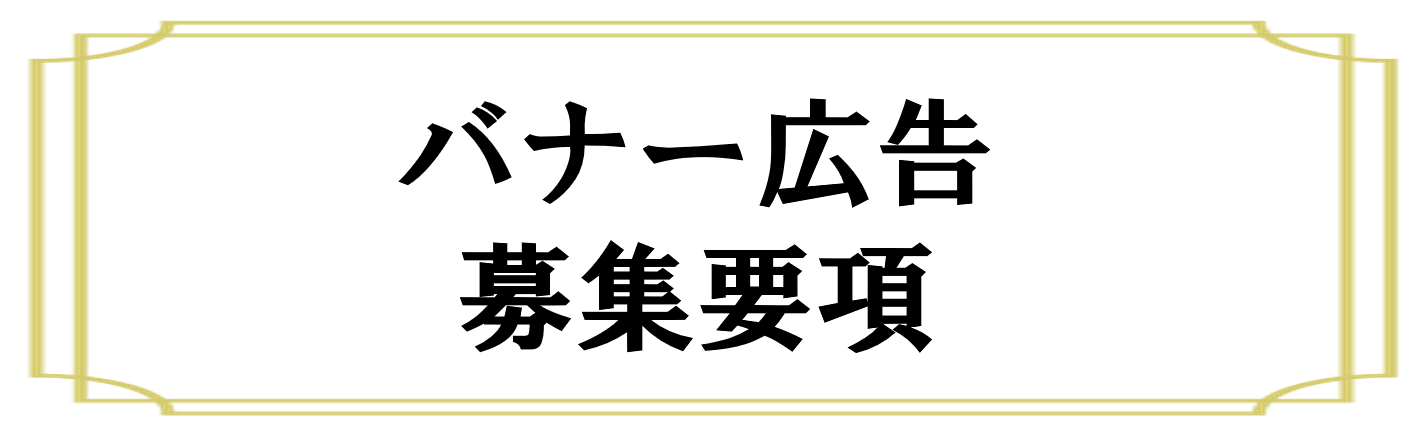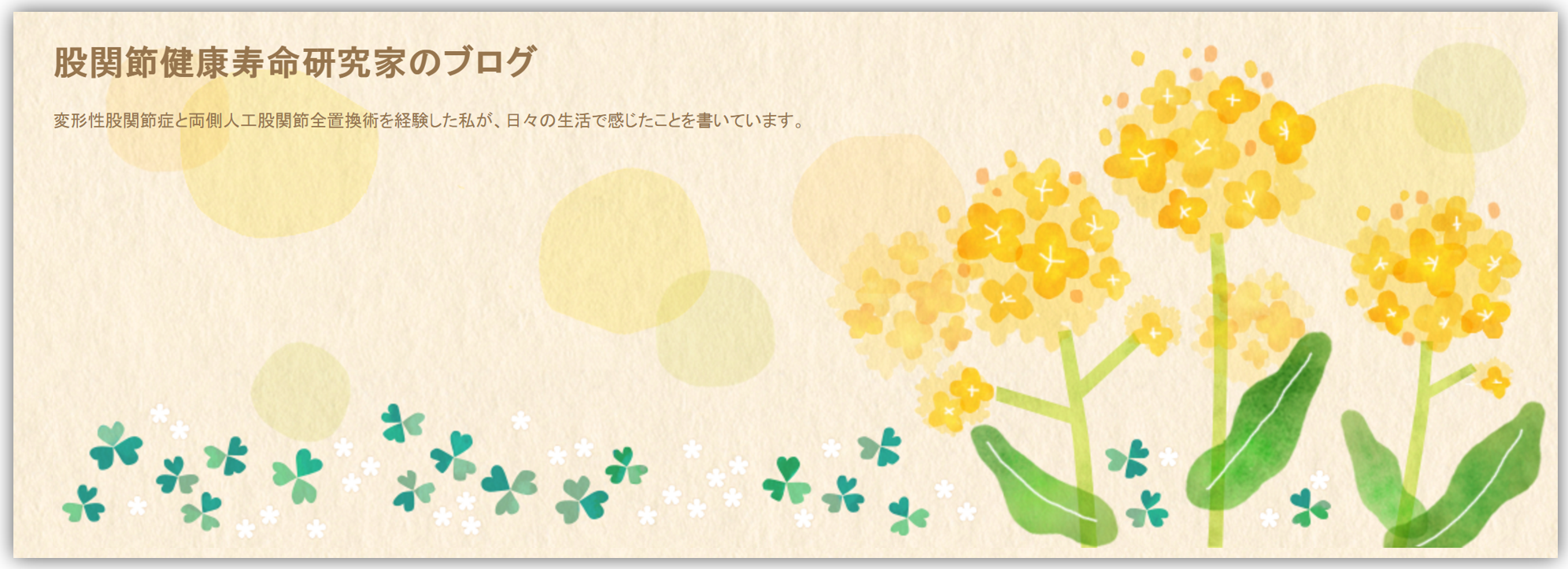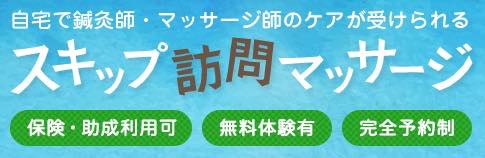変形性股関節症と正しく向き合う会の代表理事、井口です。
変形性股関節症の患者さんにとって、病気を克服し、以前のような日常生活を取り戻すことは心からの願いだと思います。
私ももちろんそうでした。
そのためにキモとなるリハビリについて、本当にたくさんの試行錯誤を行いました。
最終的に私は”リハビリの軸となる考え方”にたどり着きました。
結果、現在では以前よりももっと幸せを感じる生活を過ごすことができています。
同様に、協会でサポートする患者さんも日常生活を取り戻すことができています。
今回は、その”リハビリの軸となる考え方”についてのお話です。
実はこれまで何度もこのブログでお伝えしてきたものですが、現実ではこの考え方を根本から理解した上で実際に行動に移すことができている患者さんは非常に少ないです。
そこで、今回もう一度お伝えします。
全ての患者さんにとって非常に重要な内容ですので、ぜひご覧ください。